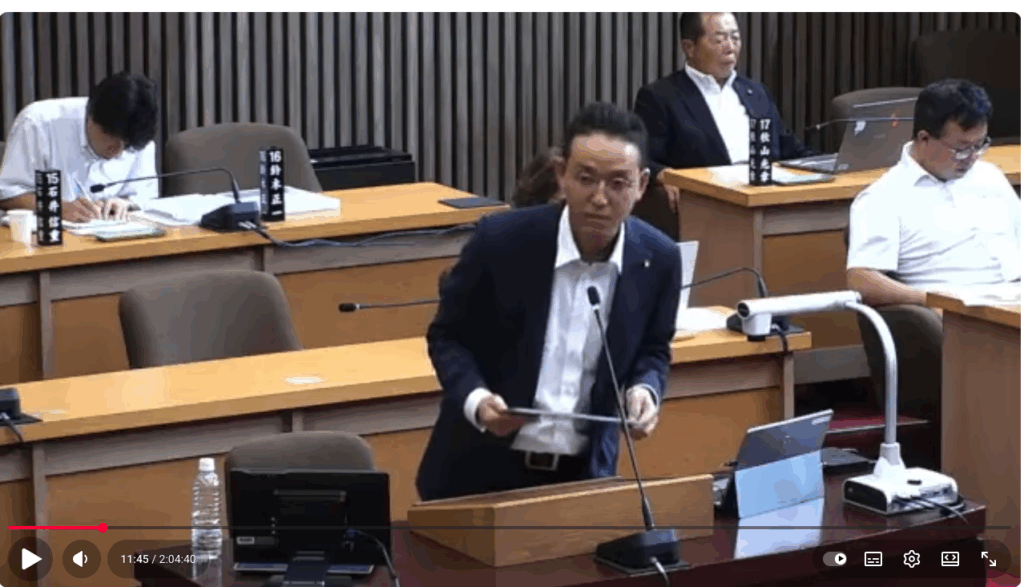
9月議会も、昨日決算審査特別委員会を終え、終盤に入りました。報告をしていきたいと思います。まずは一般質問です。
私の出番は4日13時からでした。詳しい内容については、前の記事でまとめたので、よかったらご覧ください。
以下で、動画も配信されております。
以下に、質問に対する主な答えを掲載します。
【一】持続可能な地域農業とソーラーシェアリングについて
Q1. 地域農業計画の目的と内容は何か?農家に十分共有されているのか?
A.
「地域農業経営基盤強化促進計画」は、担い手への農地集約を目的とし、農業者や地域の協議を経て策定されています。館山市は、地区説明会の開催や地図作成を通して農家に内容を共有したと認識しています。
Q2. 耕作放棄地と有害鳥獣被害の現状と対策は?
A.
令和6年度末で耕作放棄地は市内全体で177.3ヘクタール。有害鳥獣被害は年間5.3ヘクタール、被害額約2,570万円。対策としては電気柵・罠の設置、農地中間管理機構の活用、地域ぐるみの保全活動を実施中です。
Q3. 目標地図で色が付いていない農地の扱いは?
A.
色が付いていない農地は、認定農業者以外の農地であり、将来的に地域の話し合いにより新たな担い手として位置づけることが可能です。農地中間管理機構による仲介支援も受けられます。
Q4. 移住者の受け入れ体制と地域計画の役割は?
A.
移住者が就農する際は、まず農地中間管理機構を通じた農地確保が行われ、その後地域計画に組み込まれる可能性があります。地域の合意形成が重要で、農村RMOなどの体制整備が望まれます。
Q5. 農村RMOの対象地域は?館山での展開は?
A.
市内全域が対象となり得ますが、補助事業の観点では中山間地域や多面的機能支払の対象地区が中心です。農業・福祉・移動支援などを包括する農村RMOの形成を研究・促進していくとの方針です。
Q6. 農業の持続可能性には農業以外の連携も必要では?
A.
農業だけでなく、販売先確保や地域福祉との連携も不可欠であり、農村RMOのような横断的協議体の形成が、地域計画の実効性を高めると考えています。
【二】ソーラーシェアリングについて
Q7. ソーラーシェアリングと他の太陽光発電(メガソーラー等)との違いは?
A.
メガソーラーや野立ては農業と無関係な発電事業が主である一方、ソーラーシェアリングは農地で営農を続けながら上部空間で発電する方式です。営農実績の報告義務があり、農地の回復も前提とされます。
Q8. 技術革新(ペロブスカイト型太陽電池)への対応は?
A.
植物が必要な光を透過させる次世代型太陽電池の研究が進んでおり、今後の普及や価格低下が見込まれています。市としてもアンテナを張り情報収集・周知に努めます。
Q9. ソーラーシェアリングの導入支援策(国の補助金等)は検討しているか?
A.
農林水産省の「営農型太陽光発電モデル事業」などについて、生産者団体への情報提供や導入実証への協力など、地域の意向を踏まえて進めていく考えです。
【三】津波警報の際の市の対応について
Q10. 津波警報時の初動対応とその評価は?
A.
7月30日の大津波警報発表時、即座に災害対策本部を設置し、避難指示や広報が迅速に行われました。海水浴場ではライフセーバー、消防団、海上自衛隊による避難誘導が行われたと報告されています。
Q11. 避難所の状況と課題は?
A.
指定避難所7カ所を開設し、最大で1,552人が避難。空調教室の活用や熱中症対策も行いましたが、施設によっては屋外での避難者が発生し、今後の改善点とされています。
Q12. 一時避難ビルの活用と判断基準は?
A.
協定を結んだ避難ビルは、時間がない場合に自主的に使用可能とされています。今回4カ所で活用されたが、長時間避難への備えが課題として浮上しました。
Q13. 渋滞や避難ルートの課題への対応は?
A.
踏切や出口が少ない海岸線では渋滞が発生。市はこうした課題を認識し、地区防災計画の中で歩行避難の経路確認や住民との協議を進める予定です。
Q14. “渚の駅”たてやまのライブカメラの防災活用は?
A.
ライブカメラは市役所から遠隔操作が可能であり、今後の津波警報時に防災情報として活用する方向で調整中です。
【解説】
今回の一般質問では、「持続可能な地域農業」と「ソーラーシェアリング」、そして「津波警報時の初動対応と防災体制」について取り上げました。
まず、農業に関しては、「農村型地域運営組織(農村RMO)」に焦点を当てました。RMOは、小学校区ほどのエリアで、住民が自らの地域課題を解決していこうという取り組みです。単なるボランティアではなく、行政の担ってきた役割を住民が補完しながら、持続可能な地域づくりを目指す手法です。
現在、全国的には8000以上の地域でRMOが存在しますが、農村部ではその展開が少なく、国も「農村RMO」として積極的に支援を行っています。館山市も都市部と農村部が混在しており、農村RMOの対象となる地域が存在します。特に農業は高齢化や担い手不足などの深刻な課題を抱えており、単体では解決が難しい問題です。だからこそ、地域全体で支えるRMOのような仕組みが必要だと考えています。
本市では昨年度、農業に関する「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」が策定されましたが、10年後の農地利用が現在と変わらないという内容が記載されている点に懸念を抱きました。実際には農地所有者の高齢化や離農などが進行しており、実態とのギャップが大きいからです。こうした計画を実効性のあるものにするには、農業者だけでなく、地域住民全体で課題を共有し、協議の場を設ける必要があります。
その上で、持続可能な農地利用を支える一つの手法として「ソーラーシェアリング」を取り上げました。農地の上部空間にソーラーパネルを設置し、営農と発電を両立させる仕組みで、農業収入の安定化だけでなく、災害時には防災インフラとしても活用できます。地域の電力コスト削減や、ゼロカーボンシティの実現にも貢献できるこの取り組みは、RMOの活動と組み合わせることで、より実現性の高いものになると考えています。
防災に関しては、7月30日に発令された津波警報を受けた市の初動対応と、今後の課題について質問しました。市の対応は一定の評価ができますが、避難ルートの渋滞、一時避難場所の環境、暑さ対策の不備など、様々な課題も明らかになりました。特に、館山市の体育館には冷房設備がなく、真夏の避難には大きなリスクがあります。私は、移動式エアコンの導入など、現実的な対策を提案するつもりでしたが、ここはタイムオーバー。事後に担当部署にお伝えしました。
今回は、他の6議員も災害対策について質問し、大きな進展として聞けたのは、「地区防災計画」の策定だと思います。これは、地域ごとにより細かな防災や避難行動計画を作成するもので、住民一人ひとりが自分の避難経路を理解し、いざという時に迅速に行動できるようにするための重要な取り組みです。
最後に、「渚の駅」たてやまに設置されたライブカメラについても、防災目的での活用を提案しました。市役所本部からの遠隔操作による津波状況の配信や、河川情報の発信などと組み合わせれば、住民の不安解消や危険行動の抑止につながると考えています。
特に津波は、自ら命を守る行動が何より重要です。一連の質問を通して、「地域が主体的に持続可能な社会をつくっていく」ことの大切さを再認識しました。RMOに挑戦しようという地域も出てきており、私も伴走しながら知見を深めていきたいと思います。
