
今年5月の改選から所属する文教民生委員会で、10月7〜9日行政視察に行ってまいりました。初日は、岡山県美作市に今年4月開校した「樸学園(あらきがくえん)」を視察させていただきました。中国地方で初めて、不登校や発達特性を持つ子どもたちのために設立された「学びの多様化学校」です。
館山市でも現在、不登校の児童、生徒が増加傾向にあり、R5年度には小学校が34、中学校が60、合計94名と報告があります。この状況を改善すべく市は小中学校学校再編計画の中で、R9年度から「学びの多様化学校」設立へと検討を進めてます。

福田昌弘教育長、野村慎惠教育次長、そして益田剛志教頭にご対応いただきました。ご多用の中、誠にありがとうございました。
■ 学びの多様化学校とは何か
聞きなれない言葉ですが、実は制度としては2005年から「不登校特例校」として存在していました。不登校児童の増加(R5年度小中学校34万人)を受けて2023年、「学びの多様化学校」と名称を変更し、不登校というネガティブなイメージから、前向きな価値観をもたせることが狙いがあります。
2025年4月現在、全国で小学校7校、中学校35校、小中一貫校5校、高等学校11校の58校に設置されており、文部科学省は300校を目指しているそうです。
それでは、今回視察した樸学園はどのような教育活動を行なっているのでしょうか。
■ 公共施設を活用した“学校らしくない学校”

樸学園は、かつての市の支所を改修して整備された校舎です。「樸」とは「削ぎ落とされた、飾らない木」のこと。子どもたちの「ありのまま」を受け止めるという想いが、この名に込められています。
一般的な学校とは異なり、カラフルで落ち着いた空間をつくり出し、まるでカフェのような温かい雰囲気が広がっていました。

なぜ学校らしくない学校なのか。それは後述しますが、何らかの理由で学校に行けない生徒に、一歩でも足を踏み出してもらうためです。さまざまな配慮が施されていました。
開校にあたっては、もともと「特別支援学校」の設置を目指していましたが、県との協議を経て、不登校特例校(2023年「学びの多様化学校」に名称変更)としての形に転換。美作市立作東中学校の分教室として開校しました。
初年度15名の生徒が在籍し、少人数制の中で一人ひとりの特性に応じた学びを進めています。15名のうち3分の1が市外から問い合わせのあった生徒とのことです。
定員はR8年度から各学年8人を予定していますが、すでに問い合わせも多く、生徒数は増加していくのではないかということでした。
■ 「生徒が主役」の学校づくり
樸学園は、定期テストも通知表もなく、掃除も義務ではありません。一見、これまでの学校とは全く異なる仕組みですが、その根底にあるのは「生徒が主役であること」。

学びを管理するのではなく、子どもが自分のペースで、自分のやり方で学べる環境を整えています。
学校というより“居場所”に近い雰囲気の中で、どこで何を学ぶのか、自分の意思が尊重されます。また教員では教えられない領域は積極的に地域のプロを招き、地域との関わりをもちながら成長を後押ししていきます。
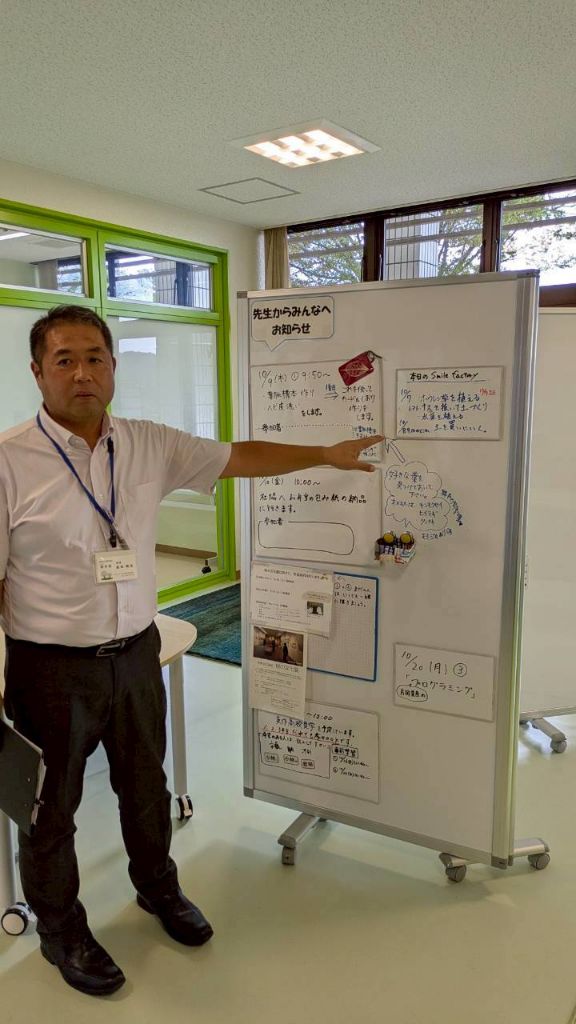
教員は“教える人”ではなく“伴走する人”。生徒の興味関心を出発点に、学び方そのものを一緒に探すスタイルです。
もともと教育を意味する英語の「education」は、ラテン語の「educere」(外へ導き出す)に由来し、「能力や可能性を引き出す」という意味合いがあります。つまり、教育とは押し付けることではなく、本質的には引き出すことなのです。
ちなみに、この点は以前書いたフィンランドの教育とも通じると感じました。
■ 医療・福祉との連携が支える
大きな特徴は、教育だけにとどまらない“包括的支援”。
心理士が常駐し、心のケアや家庭への助言を行うほか、全国でも珍しい「作業療法士(OT)」が導入されています。(米国ではすでに一般的とのこと)

発達障害などを持つ子どもが集団活動に適応しやすくなるよう、日常生活の動作や姿勢の支援、環境調整を担います。
市の「青少年サポートセンター」と連携し、登校が難しい子どもたちに対して、家庭訪問やオンライン支援なども展開。医療・教育・家庭が一体となって子どもを支える体制が整っていました。
また、重要なのは、精神科との関係です。
一昔前の精神医学の考え方に基づく医師の中には、薬の処方を中心に対応してしまい、結果的に「薬漬け」になることもあるそうです。我々は医学の専門家ではありませんが、精神の分野は未解明のことも多く、「きちっとした見立てのできる先生とつながること」が大切だと語られていました。
■ 学びを“教科”の枠を超えて
授業では、音楽や美術、家庭科などを総合的に扱う「サーチ(Search)」という独自の教科を設置。
生徒が自らテーマを決め、調べ、表現する探究型の学びが実践されています。
例えば、青虫の観察から生態を調べ、記録をまとめる。あるいは自分たちで「スマイルファクトリー」というミニ農業会社をつくり、苗を育てて販売する。支所内のレストランとも連携しているそうです。

こうした学びは教科を横断しながら、社会とつながる“生きた学習”へと広がっていました。
■ 保護者も共に育つ
「子どもだけでなく、保護者も元気でいなければ家庭は変わらない」。この考えのもと、夏休みには「ファミリーカフェ」を開催し、保護者が集って語り合う場を設けています。
家庭と学校の信頼関係が深まることで、子どもが安心して学びに向かう力も育まれていました。
実際、2年半も不登校だった生徒が、今では週1日決めて通えるようになるなど、短い期間で着実な変化が見られています。
■ 教員、生徒の募集には課題も
ここまで特筆すべき点を列記しましたが、もちろん課題も多くあります。

まずは教員です。教員は、単に教えるスキルではなく、子どもたちに寄り添い、対話を重ね、見守る力が求められるため、そうした人材を見つけるのは容易ではありません。教員不足が全国的に深刻化する中で、こうした「人間力」を持つ先生を確保することは、どの自治体にとっても大きな課題です。
また、生徒側もすぐに新しい学校に足を運べるわけではありません。
「行かない」ことを選んできた子どもたちが、「行ってみよう」と思えるまでには、家庭や学校、地域の支えが欠かせません。
だからこそ、樸学園では昨年度なんと280回を超える教育相談を行ったといいます。教育相談で、一人ひとりに丁寧に新しい学校について説明し、生徒を導いたのです。こうした地道な関わりが、子どもたちの新たな一歩につながっているのだと感じました。
福田教育長の最後に語ったひとことがとても印象的でした。
「児童が不登校となった場合、当初はなんとか登校してもらおうと学校も努力するのだが、一旦不登校が長引くと、形式的な資料のポスティングをやるぐらいで、ますます学校との距離が離れてしまう。そうではなく、樸学園という選択肢があるということを多くの方に知ってほしい。学校という枠にとらわれず、もう一度学びや社会とのつながりを取り戻す場として活用してほしい」
まさに「学びの多様化学校」が「不登校児童への支援が形骸化しやすい現状」を打破する手段であることを物語るお言葉でした。

■ 館山市でも始まる“新たな挑戦”
館山市でも現在、小学時における「学びの多様化学校」のR9年度設立に向けた検討が進んでいます。
不登校や特性を持つ子どもが増える中で、どんな形であっても「学び続けられる環境」を地域で支えることが求められています。
今回の樸学園視察で強く感じたのは、「学校に行けない子のため」ではなく、「誰もが自分らしく学べるため」の学校という発想です。
今回実践している中には、一般の学校でも取り入れたほうがよいのではと思われる教育が多く含まれていました。
■ おわりに
学びの多様化学校は、まだ全国的にも始まったばかりの新しい取り組みです。既存の学校制度に収まらない子どもたちの学びを支える仕組みとして、各地で試行錯誤が続けられています。
館山市がこうした先進的な教育モデルにいち早く参加することは、とても意義のあることだと感じました。
最初から正解を求めるのではなく、現場の声を聞きながらトライアンドエラーで進めていくことこそが大切です。
館山らしいやり方で、子どもたち一人ひとりに寄り添う教育の形を模索していく——その姿勢こそ、これからの時代に求められているのだと思います。